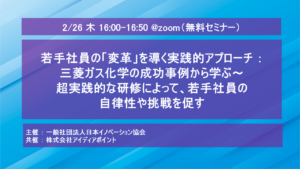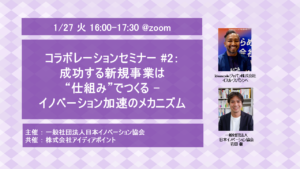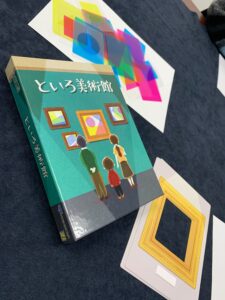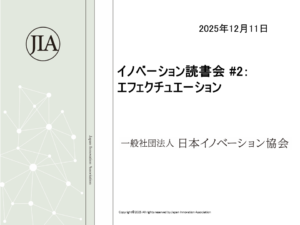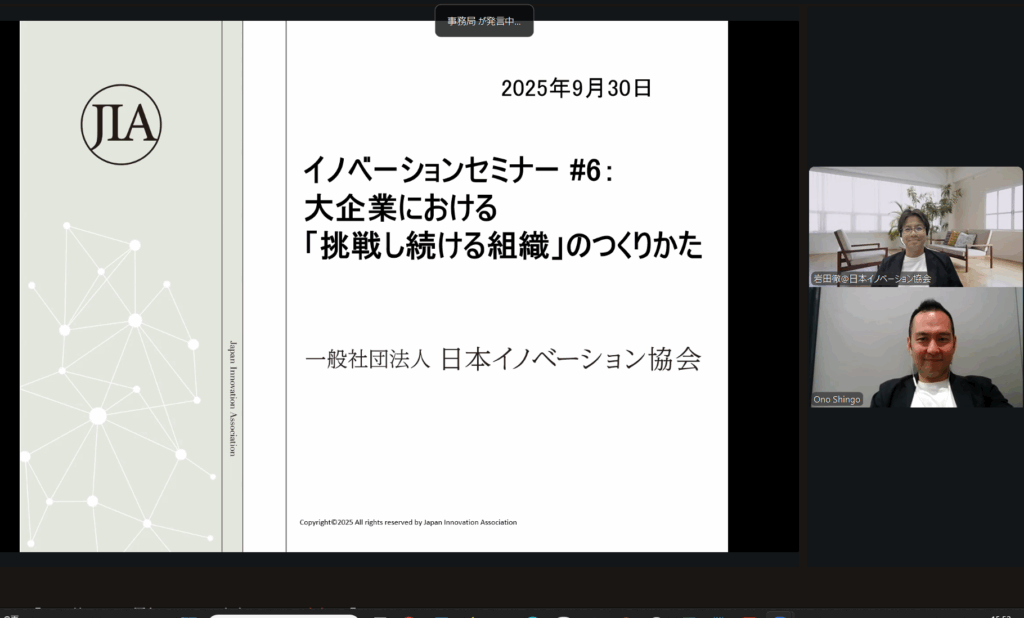
2025年9月30日(火)に「イノベーションセミナー #6: 大企業における「挑戦し続ける組織」のつくりかた」を実施いたしましたので、ご報告いたします。
現在、日本イノベーション協会では、多くの企業で取り組んでいる『新規事業』、『イノベーション』について、その経験やスキルを共有する機会を提供しています。
イノベーションセミナーでは、『イノベーションを起こす』ことに関するプロジェクトの推進経験のある方や、その支援をする方に、プロジェクトを推進する際の苦労や成功体験、『イノベーションを起こす』ために重要なことについてお話していただいています。
今回は当協会の理事であり、グローバル人材部長を経験され、現在、事業責任者として活躍されている小野 真吾氏と当協会代表 岩田の対談を通じて、人事部長と事業部長の2つの立場や視点から、「組織が挑戦する」ことに必要な要素、その取り組みやそれぞれへの期待、難しさ / おもしろさについて議論しました。
はじめに、当協会代表理事の岩田より、本イベントの趣旨と進行の説明をさせていただきました。その後、小野氏より「人事部と事業部の視点から考える挑戦し続ける組織」についてお話いただき、その後、「私たちは、「どうやって」挑戦し続けられるだろうか?」についてパネルディスカッション形式で、当日、参加者様よりいただいたご質問も交えながら、小野氏と岩田で対談をいたしました。 下記に、本イベントのサマリーをご報告いたします。
人事部と事業部の視点から考える挑戦し続ける組織(三井化学株式会社 小野 真吾氏)
- 人事と事業を往復した経験から語る挑戦し続ける組織づくり
- 小野氏の現職は三井化学株式会社のオーラルケア(歯科関係)事業の事業部長である。以前は半導体・電子情報材料の事業に従事後、人事へキャリアシフトし、グローバル人事責任者となる。2025年4月に再び事業へ戻りオーラルケア事業部長として、グローバルな事業の収益責任を負う。事業と人事を往復するキャリアを持っている
- 複業として2008年から開業し、人事コンサルタント、英語塾代表、講演 / パネルディスカッションへの登壇など様々な活動を行っている。一社所属ながら外部活動で社会に貢献する多面的な視点を持つようにしている
- 事業現場での8年間(入社後約8年)はBtoB素材事業の海外営業・マーケティングを担当した。顧客はグローバル企業で、文化・意思決定・リーダーシップ・人への投資の違いを感じた
- 人事へキャリアチェンジした背景は、事業現場から見て「人事の顔が見えない」「人事が人・事業を見ていない」という問題意識を持っていたから。経営・事業と伴走する人事のプロを目指そうと考えた
- リーマンショック後の組合交渉で賃金切り下げなどの厳しい局面を経験した。採用にも関与し新しい指標策定を試みるが、当初のHR変革はなかなか進まず悶々とした時期を過ごした
- 転機は米国人コーチとのセッションである。「君は何を恐れているんだ」という問いで初心に返った。事業を深く理解し、人をとことん知り、現場に入り、泥にまみれて伴走し、仕組み化する方針へ完全に振り切る。整えてから展開する人事から、走りながら現場でつくる人事へ転換した
- 人事3年目頃、クロスボーダーM&Aの人事リーダーを担当した。会社最大規模の買収で、グローバル22カ国26拠点を対象とした。PMOに入り、ドイツ企業と交渉した。リストラクチャリング、ホールディングスからの切り出し、グローバルなコーポレート機能の構築などに早期から参画した
- 買収後は文化統合プランの策定・ワークショップのリード、PMI(統合後の共同プロジェクト)推進した。業績・シナジーが未達時には責任追及やマネジメント間の批判が生じ、国を跨ぐコンプライアンス問題への対処や厳しい人事対応も実施した
- 新事業立ちあげの際には事業部長と協議し、採用から開始した。社内人材と買収先の人材を合わせ約50人でミッション・ビジョン・バリュー策定、戦略共有ワークショップを実施した。探索型カルチャーを設計し、強みの相互活用を促進した
- グローバルHR変革とネットワーク型組織による新規事業・M&A統合推進
- 事業伴走の中で課題解決のためM&A、新規事業設立、海外子会社設立、ベンチャー出資などを人事として支援。事業近接での実務からHR変革の必要性を再認識した
- 買収後のPMIで東京中心のグローバルHRチームを発展的に解消し、海外事業会社・地域統括会社を巻き込むプロジェクト型のバーチャル組織へ再編した
- キータレントマネジメント・後継者計画の仕組みを、2016年度から全社導入した。指名委員会との一気通貫の仕組みにした
- HR専門領域(タレントマネジメント、人事システム統合運用、リーダーシップ開発、組織開発、報酬)チームを編成し、各地域の変化に応じて企業側が支援するようにした。日本でも外資同様の体制を既存人材で構築した
- トップダウンではなくボトム・ミドルアップで根気強く巻き込みを重ね、1つずつ形にし、展開するようにアプローチをした
- 現場で優先度が高い施策を経営・事業責任者と合意し、着実に実行した
- 従業員が約1万2千人から買収で約2万人近くへ急増した。そのため、グローバルエンゲージメントサーベイを実施し、文化・組織の可視化で人材戦略遂行に貢献した
- 人事テクノロジープラットフォームを導入し、グループ130社を全統合。組織、職務、グローバルグレード、人材情報をシステム上でタイムリーに可視化した
- 人事と事業が一体で推進するグローバル構造改革とオーラルケア事業のターンアラウンド
- トップダウンではなく、ステークホルダーと対話しながら“連続トランジッション”として改善を積み重ね、数年で大きな変化を実感できた
- ドイツの世界第6位の歯科メーカーを買収した。CAD / CAM、プリンター、ソフトウェア企業へ出資、日本の国内2位のプライム上場企業へ出資した。買収企業群をグローバル統合して競争力を強化に取り組んでいる
- 人事責任者としてM&A / PMIに継続関与してきたため、事業異動前から世界中の人と事業概観を把握していた。そのため、4月に事業担当となった際、関係者は自分の存在のことを既に知っている状態だった
- オーラルケアは構造改革事業に位置づけられた。成長軌道回復を目指し、コスト改善(販売・間接人員最適化)や、グローバル拠点集約を実施中
- 事業責任者として、同時に文化変革・人と組織の再設計に注力している。コスト削減とトップライン拡大の両立を推進中
- 人事×事業の視点:同じ事象を異なる言葉で扱うが本質は共通している。事業の持続的成長と社員のやる気最大化が目的である。HRBPと事業責任者は立ち位置は違えど、共通の土壌に立つべきである
- 事業現場への深い理解をもつ人事が必要である。解決策が未確定でも伴走し、一緒に学び・調査・実行する姿勢が重要である
- 人事はビジネスモデルへの強い興味と学習が不可欠である。事業ポートフォリオに合わせた人材ポートフォリオ・組織設計を行い、仕組みは“後工程”として整えるのが適切であるくらいの感覚でアジャイルに動く事は必要
- 制度運用だけでなく、現場・人・事業を知る人事が現場社員の強いパートナーとなる
- HRBPが事業に踏み込めない要因:①人員不足と多忙で現場に行く時間がない、②事業について学ぶことはなかなか難しく、現場に飛び込む心理的ハードルが高い
- HR視点での事業理解・実践的学習とリーダーシップによる変革
- 現場社員に近づくため、毎日「オフィスグリコ」のお菓子ボックスに行き、アイスクリームを購入して昼休みに現場社員の席で食べて、交流を拡大した。人事所属であることを伝えつつ、M&Aや企画担当者と関係構築を進めた
- M&A参入に向けて法務で関連書籍を借りて学習し、成立済み案件の契約書を見せてもらいトランザクションの立て付けを実務的に理解した。その後、企画側へ「プロジェクトがあれば参加したい」と能動的にアプローチした
- 事業モデルに応じて人・組織のあり方は変わるため、制度中心の固定観念を離れ、ビジネスを実現するための人材・組織設計を学ぶ必要性がある
- 施策導入自体が目的ではなく、施策を通じた事業成長が目的である。トランスフォーメーションのモデルや企業の発展段階の過程で陥りやすい罠は論文等で体系化されているため、一度概観し思考手法を得る良い
- HRが事業理解を深めるためのおすすめの学習方法:①事業戦略モデル(3C、5フォース、環境分析、財務)を把握する。②現場で戦略・予算を踏まえキーパーソンの声を直接収集する。③HRモデルのフィロソフィーを学び、施策の効く条件と意味を理解して根拠ある提案を行う
- 最終的にはリーダーシップが鍵である。個人のリーダーシップに他者が共感し追随する。変革と創造に挑戦し、不確実性の中で常識化前の一歩を踏み出す勇気が重要だと考える
- 見えない状態から1%の可能性を見出す「未来を見る思考」は勉強だけでなく、同じ対象を多様な視点で捉える訓練の習慣化が重要
パネルディスカッション(という名のぶっちゃけトーク) – 私たちは、「どうやって」挑戦し続けられるだろうか?
- 人事と事業の橋渡し、統合・分散戦略、財務リテラシー
- 事業部長の役割は数字へのコミット。利益・PL統制・予算進捗などを厳格に管理する。短期成果と将来の成長の両立が難しいところで、結果を出すためにあらゆる手段を講じる現実主義的なところが必要である
- HRBPは現場に必然的に行くが、コーポレート / シェアード人事は現場との接点が少ない。事業・経営に近い人が交流の場を作り、例えば週40時間のうち2時間を新しい人と会う・現場に行くなどに意図的投資(年間約100時間)することを推奨する
- 日本企業はメンバーシップ型・労働法・文化の違いからグローバルな拠点の統合が難しく、統合の意味を出せないとコミュニケーションコストが増え、成果が出にくい。事業モデルにより統合 / 分散の最適は異なる
- 競争相手が欧米・中国・アジアなどのグローバル企業で、統合分散を設計できるプラットフォーム / OSを持つ企業と比較して勝てるかが鍵である。テクノロジーやAIを活用し効率的プラットフォームを持つかで将来投資・成長が変わる。グローバルで戦うなら自社も変革しないと持続的成長が困難である
- HRBPが最低限学ぶべきこととして、財務・会計(PS/BS/PL/キャッシュフロー)がある。また、事業伴走で実務題材に基づく学習(OJT的)も有効である。ROIC資本効率改善の選択肢を理解しないと提案・提言ができない
- HR業界は「学びの宝庫」
- HR業界は学び続けることが必要で、価値提供志向が高い「学びの宝庫」。課題は経営戦略・事業戦略とのリンク感覚の醸成である。事業側は人事と対話し、困りごとを共に考える姿勢も重要である
- HRで事業部出身者が成功しやすい理由は、現場でのジャグリング(同時課題処理)に慣れているためである。HRは制度整備から入ることが多いが、小規模事業で「整える間もなく全部やる」体験をすれば、(部署の)出身に関係なく成長可能である
- 事業部と人事部の両方でトライアンドエラーを重ねて得た一人の意見として、少しでも参考になれば嬉しい。成長にはトライとエラーが不可欠。HRやHRBPは小さな一歩を重ね、少しずつはみ出して挑戦することが大事である
実施後に参加者からいただいたお声として、「人事を経験し、事業部長をされている生の声は参考になった。コーポレート人事を担っている中で、積極的な事業への関わり方、人との接し方を模索していきたい。」、「事業と人事の両方の視点から、戦略・組織開発についてお話いただきました。実際にどのように事業を知っていったかも聞けて、非常に参考になりました」などのご意見をいただきました。
ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!
今後とも継続的にセミナーを実施していきますので、ご興味のある方は、ぜひ、ご参加ください。
本記事に関するご質問やコメント、疑問に感じた点がございましたら、ぜひ、お問い合わせフォームよりご連絡ください。最後までお読みいただきありがとうございました。
一般社団法人日本イノベーション協会
事務局
高橋佑季