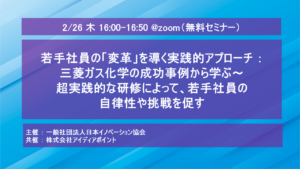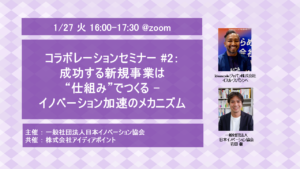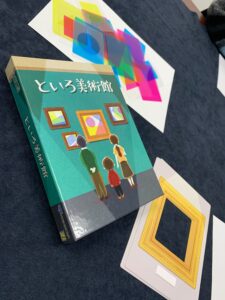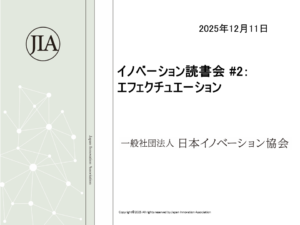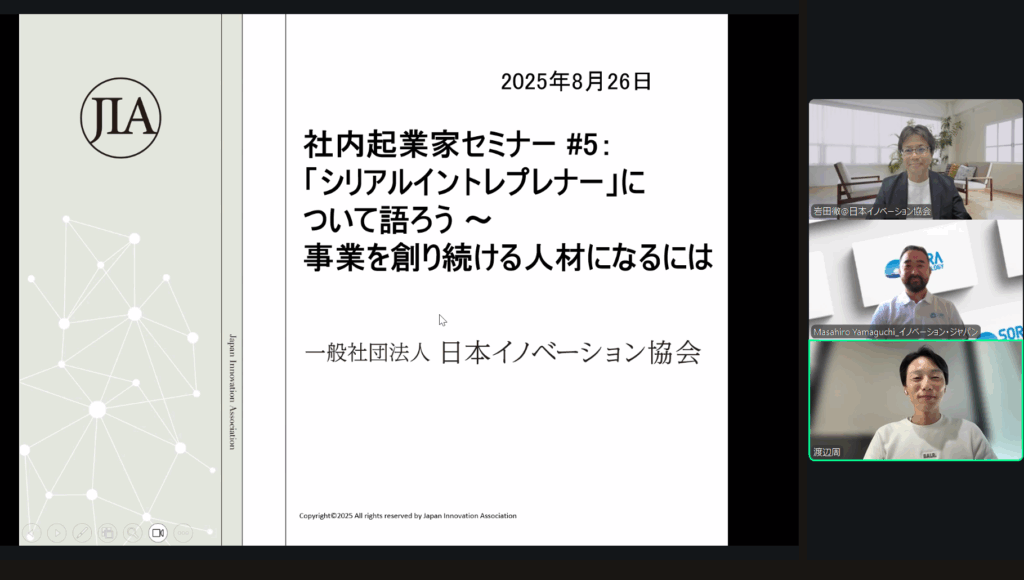
2025年8月26日(火)に「社内起業家セミナー #5: 「シリアルイントレプレナー」について語ろう ~ 事業を創り続ける人材になるには」を実施いたしましたので、ご報告いたします。
現在、多くの企業では、『新規事業の創出』が経営上の課題となっています。社内では専門部署の設立、新規事業提案制度等の社内での施策が進められている一方で、新規事業創出に向けてチャレンジして、実際に立ち上げたことのある経験者のお話を聞く機会は多くありません。
本セミナーでは、実際に、大手企業で新規事業の立ち上げに取り組んでいる方をゲストにお招きしてアイディアの発想から、社内起業のきっかけ、どのように事業を立ち上げているのか、その経験をお伺いしております。
今回は、新規事業創出を支援している一般社団法人イノベーション・ジャパンに所属され、自らも大手企業で多くの新規事業を生み出してきた渡辺氏、山口氏をゲストに迎え、新規事業を創出してきたご経験をお話しいただくとともに、事業を創り続ける「シリアルイントレプレナー」について議論いたしました。
はじめに、当協会代表理事の岩田より、本イベントの趣旨と進行の説明をさせていただきました。その後、渡辺氏、山口氏より「自己紹介 & それぞれの新領域開拓ストーリー」についてお話いただき、その後、「「シリアルイントレプレナー」 ~ 事業を創り続ける人材とは」についてパネルディスカッション形式で、当日、参加者様よりいただいたご質問も交えながら、お二人と岩田で対談をいたしました。
下記に、本イベントのサマリーをご報告いたします。
自己紹介 & それぞれの新領域開拓ストーリー(一般社団法人イノベーション・ジャパン 代表理事 渡辺 周 氏)
- イノベーションジャパン / 渡辺氏の自己紹介・農業×新規事業の取り組みと今後の挑戦
- 一般社団法人イノベーションジャパンの紹介。ビジョンはイントレ / アントレプレナーの連携で世界を変える。知と経験の共有(セミナー等で情報発信)、育成支援(イノベーション人材・企業/自治体の新規事業支援)、ネットワーキング(プロフェッショナル/アカデミア交流)などの活動をしている。設立2021年。メンバー7名。大企業のイントレプレナー、スタートアップ代表、ロボティクス、ソーシャル、農業(渡辺氏)など新規事業の専門家が参画
- 渡辺氏は、20代はキヤノンで半導体 / 液晶製造装置のレンズ・機械設計と技術営業。30代〜40代前半はNECでCSRや事業開発。2025年5月からNTTデータで事業開発をしている。ミッションは日本の技術で途上国の発展・産業創出。一次産業の発展を通じた暮らしの豊かさ向上。専門領域は新規事業×農業×グローバル
- 2011年3月11日の震災後、宮城県山元町でボランティア、農業とまちづくりの復旧/復興に携わる。2012年にNPO設立後、農業生産の株式会社を設立。プロボノとして資金調達や事業開発を担当。翌年にハウスを建て、いちご生産を開始
- 震災翌年、いちごブランド『ミガキイチゴ』を立ち上げ、伊勢丹で展開。加工品開発も推進。2019年頃にいちごスイーツカフェ『ICHIBIKO』を企画、都内約10店舗展開。
- 2013年頃からインドで農村の農業発展・所得向上に取り組み。ヨルダン、マレーシア等でも生産や中東向け輸出を推進し、新規事業を連続創出
- NECでのスマート農業:社内のアグリテックグループに戻り、CropScopeのトマト展開(クロップスコープ)の企画・開発・普及を推進。カゴメ株式会社とポルトガルで、合弁会社を設立(2022年9月inポルトガル)。加工用トマトのAI営農支援を全世界で積極的に展開。営農支援に灌漑・施肥の自動化などを加え、さらなる営農の効率化を目指す
- 2025年5月からNTTデータの事業部で新規事業立ち上げに参画。テーマは引き続き農業領域
自己紹介 & それぞれの新領域開拓ストーリー(一般社団法人イノベーション・ジャパン 理事 山口 真広 氏)
- マラリア対策とソーシャルイノベーションに基づく新規事業開拓(個人キャリア遍歴とドローン×AIによるLSM)
- 山口(モスキート理事/“Chief Mosquito Officer”)。イノベーションジャパンではチーフモスキートオフィサー(CMO)という新しい肩書きで活動しており、外国人にもクスッとされる「謎のタイトル」として活用している
- 英国で修士号取得後、国連を目指すも、当時流行し始めていたテクノロジーやイノベーションを用いて社会課題を解決し、それを事業化する潮流(ボトム・オブ・ザ・ピラミッド)に強く共鳴した
- ガーナ農村の栄養改善プロジェクトで味の素の現地駐在中に活動を目撃。「俺たちがなんとかしなきゃいけねえぜ」と、一つ一つは安価ながら利益を上げつつ持続的に事業を行う味の素社員の姿に感銘を受けた。国際機関の寄付依存型とは異なり、お金が尽きたらプロジェクトが終了する業界とは全く違う面白さを感じ、国連への応募を取りやめ、企業への就職を決意した
- 当時アフリカビジネスに注力していた住友化学に入社し、マラリア事業に出会う。殺虫成分が樹脂に練り込まれ、5年間徐々に放出される蚊帳(WHO承認)を大量配布する事業に従事。始まって以来、累計約3億針を配布した。マラリアは年間約60万人を死亡させており、約20年前までは年間100万人規模で亡くなっていた。アフリカの人口は約10億人規模と認識されている。公共調達においては、配布量を最大化したいWHOや国際機関と、企業の収益確保との間で持続性の確保が揺らぐ課題に直面した
- この課題に対し、蚊帳をリブランディングしてスーパーマーケットで販売する試みを開始。また、同じテクノロジーを応用し、デング熱対策として東南アジアで網戸(昼に媒介する蚊に効果的)を展開。さらにコールマンとコラボレーションし、テントなども開発した
- これらの新規事業は「10億円」規模に成長し、収益もそこそこ得られた。しかし、公共調達事業と比べると規模が小さく、事業バランスが課題となった。事業が拡大期に入ると、大企業のあるあるとして、運営に長けた別の担当者へ引き継がれた
- 次の新規事業を模索した。マラリア撲滅のため、蚊帳事業で協力した方の「蚊帳の次に来るのはボウフラ対策だ」という示唆を受け、「ボウフラ対策」に着目。1年かけて役員と協議したが、実績がないことを理由にアカデミアとの協業に留まり、社内承認が得られなかった
- 2018年頃、自動運転やCASE、MaaSといった言葉が流行し始めた「モビリティ大変革時代」を背景に、タイヤという無骨な分野に面白みを感じた。敢えて新規事業が起こりにくいと思われた領域で何かを起こすという理由で、ブリヂストンに転職
- コロナ禍の制約下で、AIの進歩によりロボットの知能は高まる一方、物理的なロボットが日常生活で役立つ存在として普及していない課題を認識。従来の「でかくて強くて早くて休まない」といった決められた動作をこなす硬いロボットの限界に対し、ブリヂストンのコア技術であるゴムの『柔らかさ』に着目した
- 人工筋肉技術に出会う。バナナのような形状のアクチュエータに空圧や油圧を注入し、周囲の繊維で拘束することで、通常は膨張するところを収縮させ、力発生を伴う筋肉的な動作を実現する技術
- ロボットの知能や認識が高まる一方で、ロボットの手には繊細さや器用さが不足している現状があった。従来のロボットハンドが部品ごとに特注(ワンメイク)で汎用性に欠ける課題に対し、人工筋肉を用いて『何でも持てる手』を多数試作し、人間の手でもロボットハンドでもない、世界初の人工筋肉製ロボットハンド『第三の手』として事業化。ブリヂストンソフトロボティクス事業を立ち上げた
- 全身を委ねて甘えられる『トトロのような存在』をコンセプトに、無目的な空間『ロボットMorphin』を企画。「サウナの次にある大人が甘えるを叶える場所」として、目的が溢れる現代社会において『無益なものに価値がある』というコンセプトを掲げ、新しいロボット2台を開発した
- 40歳を迎え、自身のキャリアパスを再考。原点回帰としてアフリカへの再挑戦を決意。Sora Technologyへ転職した。Sora Technologyは、ドローンとAIを活用したマラリア対策企業。LSM(幼虫対策)として、自社開発のドローンが水域を効率的にスキャンし、独自のAIシステムが水温や濁度などの要因から繁殖地となる可能性を判断。高リスクと特定された箇所のみに殺幼虫剤を散布する
- マラリアは年間約2億人が感染し、60万人が死亡、その95%がアフリカで発生している。アノフェレス蚊の刺咬によって伝播。既存の蚊帳や室内スプレーは成虫対策であり、幼虫の発生を根本的に止められない。幼虫発生源対策(LSM)は有効な手段であるものの、費用対効果の低さ、多大な人手、殺幼虫剤の大量消費、環境への悪影響が課題。Sora TechnologyはドローンとAIでこれらの課題を解決し、効率化と負荷低減を実現する
- 最近、万博会場での委託業務を受注。ユスリカが大量発生していたが、専門家でも発生源の特定は困難。蚊も含め、上空からの写真撮影でデジタルマップを作成し、AI解析によってユスリカや蚊の発生源を推定。その後、専門家と連携して発生源を特定し、対策を講じる
- 万博会場の対象範囲は「大体1キロ四方」で、水たまりなどの撮影を約2時間で完了し、その後AIで解析を行う。AIがピンポイントで発生源の候補を絞り込むため、多くの候補は出ない
- 発生源は「水たまり」「溝」「側溝(食付け)」など。現地にはトラップが仕掛けられており、そこで蚊を捕獲(個体確認)したデータと組み合わせて検証する
- 薄いマスや定常的に水が溜まる場所に薬剤を散布しても蚊が発生し続ける『なぜ』を、空撮データ、AI解析、トラップによる捕獲データ連携によって解決に導く
パネルディスカッション(という名のぶっちゃけトーク) – 「シリアルイントレプレナー」 ~ 事業を創り続ける人材とは
- 大企業とベンチャーにおける新規事業開発の組織文化とプロセスの違い
- 大企業で新規事業開発のプロセスを構築する際の課題は、人事評価制度にある。売上だけでなく、仮説検証の回数や失敗からの学びを評価する制度の導入が重要だが、定着には少なくとも5年はかかる
- 大企業とベンチャーでは、事業のスピード感や文化が大きく異なる。大企業は意思決定が緩やかだが、ベンチャーは即戦力を数日で採用するなど非常に速い。また、大企業からベンチャーへ移ると、相談相手が少なく、自身で決断する場面が増える
- アフリカは国ごとに市場が異なり小さいが、三大感染症(マラリア、エイズ、結核)だけで1兆数千億円規模の巨大市場が存在する。ビジネスを大きくするには、国際機関を巻き込み、トップに直接アプローチするようなスタートアップ的な動きが求められる
- テクノロジーを活用した新規事業の事例として、ドローンとAIによるマラリアの発生源予測や、農業分野での事業開発が挙げられた。農業は作物のサイクルに合わせる必要があり、実証が年に1〜2回しかできず、事業化に3〜4年かかるという時間軸の違いが課題となる
- 大企業での新規事業推進とマラリア対策の歴史
- 大企業での新規事業は、社内理解の得にくさや意思決定の遅さが課題。特に日本では海外より動きが遅い傾向がある。事業への「思い」を持つ人は、組織に「ノー」と言われても粘り強く続けるが、評価のためにアサインされた人は諦めやすい。大企業の新規事業は楽しそうな雰囲気がある一方、3年ほどで担当者がいなくなることも多いという
- 書籍『日本人ビジネスマンアフリカで蚊帳を売る』は、住友化学のマラリア対策約40年の歴史を実名で綴った記録。殺虫剤を練り込んだ蚊帳「オリセットネット」はWHOに評価され、世界基金の設立にも繋がり、20年でマラリアの年間死亡者数を100万人から50万人に半減させた。この成功事例は、現在の事業のバイブルとされている
- かつてのマラリア対策では、蚊帳を殺虫剤に浸す手間があったが、住友化学の「オリセットネット」がこれを解決した。現在では、飛行距離1kmの蚊の幼虫対策として、従来は不可能とされていた広範囲の水たまり探索と薬剤散布を、ドローンとAI技術で実現しようという新たな挑戦が進められている
- ベンチャーの事業開発とアグリテックの展望
- アフリカのBtoBアグリビジネス、特にテクノロジー分野はまだ市場が確立しておらず、案件規模も小さい。この状況を打開するため、自社でのサービス開発に固執せず、M&Aや海外・現地企業との連携を積極的に行い、事業の「面を取る」戦略が重要となる。地理的、ソリューション的に補完関係を築き、事業規模を拡大していくことが鍵となる
- 農業の生産性向上にはデータ活用も一側面としてあるが、農家にとっては数万円レベルのアグリテックより、1000万〜5000万円規模の投資となる農業機械の方が優先度は高い。農業機械は市場規模も生産性への影響も大きく、データだけで解決できることには限界がある。依然として属人的な産業であり、完全な自動化は容易ではない
- 第一次産業(農地、森林など)が持つGHG削減といった「環境価値」のビジネス化に注目している。日本ではJ-クレジット等の仕組みはあるものの、市場規模が小さく、また農業分野のGHG排出比率が約5%と他国(例:2割の国も)に比べて低いため、ビジネスの進展は遅い。これが生産者の新たな収入源となる可能性を秘めている
- 「遺伝子組み換え蚊」の技術に注目。人を刺すメスと交尾しても卵が孵化しなくなるよう遺伝子操作したオスを放つもので、既にブラジル等で効果を上げている。従来の殺虫剤や、特定の昆虫にのみ効く「生物農薬」と並ぶ第3の選択肢として、各国がどう導入していくかに関心がある。技術の進化は非常に速い
- 大企業におけるアグリテック事業戦略、新規事業開発
- アグリテック事業では、現地の企業(商社、財閥など)との連携が不可欠。自社はAIやインフラなど一部に特化し、スピード感を重視すべき。多くのアイディアは既存のものであり、事業規模や自社の役割を基準に10〜50個のアイディアを素早く評価することが重要。個々の農家へのヒアリングだけでは、輸出拡大のような大きな事業構想は生まれにくい
- 書籍「忍者イノベーション」を引用し、既存事業と新規事業の違いを解説。既存事業が領地を守る「武士」であるのに対し、新規事業は敵地に潜入し情報を持ち帰る「忍者」に例えられる。失敗しても必ず生きて情報を持って帰ることが任務であり、行動力をもって深く潜入し生還する人材が新規事業に向いていると述べられた
実施後に参加者からいただいたお声として、「めちゃくちゃ面白かったです。ありがとうございました。どうしてそういう行動が取れるのか、原動力についてもっと聞いてみたいと思いました。」、「登壇者の行動力に感銘を受けました。少しでも近いマインドに変えていきたいと思います。」などのご意見をいただきました。ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!
今後とも継続的にセミナーを実施していきますので、ご興味のある方は、ぜひ、ご参加ください。
本記事に関するご質問やコメント、疑問に感じた点がございましたら、ぜひ、お問い合わせフォームよりご連絡ください。最後までお読みいただきありがとうございました。
一般社団法人日本イノベーション協会
事務局
高橋佑季