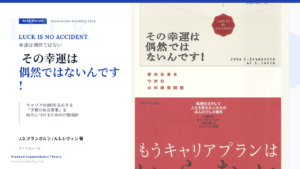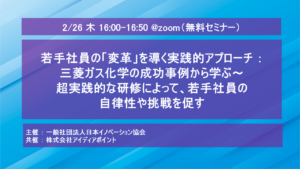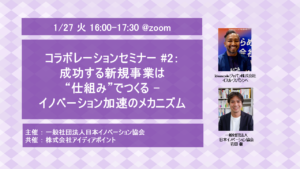2025年3月12日(水)に「イノベーションセミナー #4: ウェルビーイング×イノベーションが世界を変える」を実施いたしましたので、ご報告いたします。
現在、日本イノベーション協会では、多くの企業で取り組んでいる『新規事業』、『イノベーション』について、その経験やスキルを共有する機会を提供しています。イノベーションセミナーでは、『イノベーションを起こす』ことに関するプロジェクトの推進経験のある方に、プロジェクトを推進する際の苦労や成功体験、『イノベーションを起こす』ために重要なことについてお話していただいています。
第4回目のテーマは「ウェルビーイング×イノベーションが世界を変える」です。今回は当協会の理事であり、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授、武蔵野大学ウェルビーイング学部長・教授の前野 隆司氏と当協会代表 岩田の対談を通じて、「ウェルビーイングとイノベーション」について議論しました。当日の様子について報告いたします。
はじめに、当協会代表理事の岩田より、本イベントの趣旨と進行の説明をさせていただきました。その後、前野氏より「ウェルビーイング・イノベーションが世界を変える」についてお話いただき、その後、「ウェルビーイングとイノベーションの現在地」についてパネルディスカッション形式で、当日、参加者様よりいただいたご質問も交えながら、前野氏と岩田で対談いたしました。
下記に、本イベントのサマリーをご報告いたします。
ウェルビーイング・イノベーションが世界を変える
- ウェルビーイングとイノベーション
- ウェルビーイングが社会の発展に重要であり、イノベーションを通じて心の健康や環境問題を解決する必要がある
- 幸せな人々は創造性が高く、社会的つながりを強化し、レジリエンスを向上させることができるとされている
- ウェルビーイングを重視することで、個人とコミュニティが繁栄し、より明るい未来を創造できるとされている。ウェルビーイングは生産性と創造性を向上させ、社会的コストを削減する効果がある
- 幸せな人は創造性が高く、視野が広く、利他的であるとされ、ウェルビーイング教育が重要である。社会課題を解決するためのイノベーションを促進することが求められている
- 社会課題解決と持続可能な未来
- 人類の未来を考えると、創造性、視野の広さ、利他性が重要である。環境問題や戦争、貧困問題に対処するためには、格差を縮小し、より良い社会を目指す必要がある
- 石坂産業の石坂典子氏は、産業廃棄物処理を通じて環境問題に取り組んでいる。リサイクル率97%を達成し、ゴミを高く買い取ることでビジネスを成り立たせている
- ボーダレスジャパンは社会課題解決に特化した会社で、ひとつの社会課題解決で1億円以上のビジネスを目安に、それを100個つくることを目指して活動している。例えば、カンボジアの布を使った商品を世界中で販売し、雇用を生み出している
- ウェルビーイングと社会課題解決のビジネスモデル
- ウェルビーイングとイノベーションの融合は、創造性を高め、社会課題を解決する新しいビジネスモデルとして注目されている
- 利己と利他を対立させず、自利利他円満を目指すことで、持続可能なビジネスが可能になる
- ウェルビーイングを考慮した製品やサービスの設計が、幸せを増進するための鍵となる
- ウェルビーイングとその産業化に向けた取り組みと課題
- ウェルビーイングを考慮した製品やサービスの開発が進んでいない現状について議論されている。特に、組織づくりや地域づくりは進んでいるが、製品やサービスづくりは遅れている
- ウェルビーイングアワードの設立。ウェルビーイングを埋め込んだ商品を評価し、広めることを目指している
- 全ての企業がウェルビーイング産業にシフトすれば、巨大市場が形成されると考えられている
パネルディスカッション(という名のぶっちゃけトーク) – ウェルビーイングとイノベーションの現在地
- 前野先生が研究者として、「ウェルビーイング」に注目した経緯
- 「自然とそうなった」というのが本当のところ
- 心の問題とテクノロジーの融合が重要と考えた
- 行動経済学や感性工学のように、心と他分野の組み合わせが発展すると予測
- 日本はウェルビーイング研究が遅れており、先行研究が必要だった
- 日本におけるイノベーションの課題
- 「破壊的イノベーション」と「持続的イノベーション」の概念があるが、日本ではゼロから新しいものを生み出すことが難しい
- 「イノベーションかどうか」の議論はあまり重要ではなく、より良い変化を生み出すことが本質
- 日本企業は内向き志向が強く、イノベーションが生まれにくいのではないか
- ウェルビーイングと人的資本経営
- ウェルビーイングが「人的資本経営」や「働き方改革」の枠組みに収まり、型にはまりがち
- 企業の経営者がウェルビーイングを外向きに活用するためには、従来の枠の中で考えると成果は限定的
- 日本企業の構造的課題
- 新入社員はキャリア自立の意識を持っているが、就活・新人研修で均一化され、指示待ちの姿勢が強まる
- 「言われたことをやる文化」がイノベーションを阻害している
- 柔軟で主体的な働き方を促進することが重要
- 幸せな会社の特徴
- 実際に「幸せな会社」は少なく、「幸せな会社」には、特定の企業には共通点がある
- 理想的な家族のような企業文化があり、社員が生き生きと働いている。
- 幸せな会社は取引先や顧客にも良い影響を与え、幸せのネットワークを形成する
ウェルビーイングはイノベーションを起こすことに密接に関係していることが良く分かる内容でした。また、様々な場面で「ウェルビーイングな状態」を作り出すことで、よい会社・組織づくりに繋がり、ひいては、よりよい社会を作り出すことに繋がることが印象的でした。
実施後に参加者からいただいたお声として、「多くの企業が「イノベーション×ウェルビーイング」を取り組む前段階にいます。本来ならば、専任を作るのではなく一人ひとりがその種になるべきですが皆に余裕(余白)なく、推進するための部署を作ると真面目にやり過ぎて発散出来ず。どこを突くとメカニズムが動くのだろうと考えながら拝聴していました。考える機会をいただき、ありがとうございました」などのご意見をいただきました。ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!
今後とも継続的にセミナーを実施していきますので、ご興味のある方は、ぜひ、ご参加ください。
本記事に関するご質問やコメント、疑問に感じた点がございましたら、ぜひ、お問い合わせフォームよりご連絡ください。最後までお読みいただきありがとうございました。
一般社団法人日本イノベーション協
事務局
高橋佑季