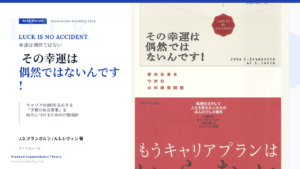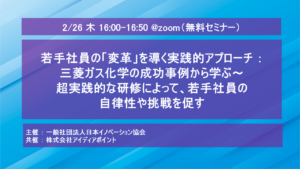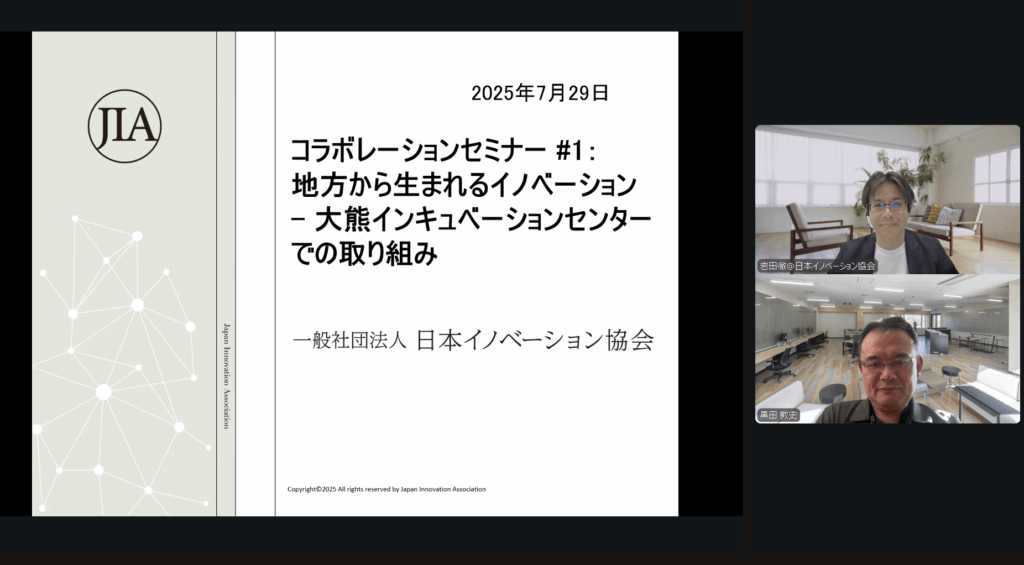
2025年7月29日(火)に「コラボレーションセミナー #1: 地方から生まれるイノベーション – 大熊インキュベーションセンターでの取り組み」を実施いたしましたので、ご報告いたします。
現在、多くの企業では、『新規事業の立ち上げ』が経営上の課題となっています。新規事業に関する専門部署の立ち上げ、社内提案制度の構築、事業部における新分野開拓の取り組みが進む一方で、社内の活動だけでは必ずしも『成果』があがっていないのが現状です。本セミナーでは、『外に出て、人に会い、対話する』をテーマに、様々な場所、立場で活動しているビジネスパーソンをお招きして、新規事業に対する取り組みについてお話いただきました。
今回は2022年に福島原発事故の発生地である大熊町に「大熊インキュベーションセンター」を設立し、インキュベーションマネージャーを務める株式会社フューチャーアクセスの黒田 敦史氏をお招きし、「地方から生まれるイノベーション」について議論いたしました。
はじめに、当協会代表理事の岩田より、本イベントの趣旨と進行の説明をさせていただきました。その後、黒田氏より「『起業』ストーリー」についてお話いただき、その後、「地方と復興の現場から – イノベーションは『辺境』で生まれる を議論する」についてパネルディスカッション形式で、当日、参加者様よりいただいたご質問も交えながら、黒田氏と岩田で対談をいたしました。
下記に、本イベントのサマリーをご報告いたします。
『起業』ストーリー(株式会社フューチャーアクセス 代表取締役 黒田 敦史氏)
- 福島県大熊町の復興と新産業創出プロジェクト
- フューチャーアクセス代表の黒田氏は、パナソニックやATカーニーなどを経て2013年に独立。大企業の新規事業や約200社のスタートアップを支援後、2019年から福島県大熊町の復興に携わる。町の産業創出方針の策定からインキュベーションセンターの運営まで担当し、2023年には住民票を移して本格的に活動している
- 黒田氏が現在注力するのが、福島第一原発のある大熊町の新産業創出プロジェクト。震災で全町民が避難したが、2019年以降段階的に避難指示が解除。役場、住宅、商業施設、ユニークな学校が新設され、人口は1000人弱に回復。トヨタなど7社による工場も稼働し、約100名が働いている
- 2022年6月に避難指示が解除されたJR大野駅周辺の中心市街地は、一度更地にされた後、再開発が進行。2025年3月には産業交流施設「CREVAおおくま」と商業施設「クマSUNテラス」が開業し、新たな町の中心地として復興が進んでいる
- 大熊町の復興と企業誘致の現状
- 駅前の再開発は第一工事が完了し、スーパー、ホテル、図書館などが建設予定。最先端かつ大規模な開発が特徴で。民間の建物も増え、短期間で新しい街が形成されている
- 2022年に開設し3年目となる大熊インキュベーションセンターは、旧小学校を改装した施設。入居企業は当初の30社強から約150社に増加。入居企業の8割がスタートアップで、その多くが先端技術を持つディープテック企業である
- 企業進出の主な目的は、町内での自社サービスの「実証実験」。町の魅力は「急成長しつつもしがらみが少ない環境」、「多様な優遇制度」、「手厚い起業支援体制」の3点。ゼロベースで理想の街づくりに関われる点が企業を惹きつけている
- 町の人口は約1500人に増加。住民票を持つ約1000人のうち、元々の住民が約400人、新規移住者が約600人と移住者が上回る状況。特にこの2、3年で急激に人口が増加している
- 国の「福島イノベーション・コースト構想」により、浜通り地域では手厚い支援が受けられる。廃炉、ロボット、エネルギーなど六つの重点分野で事業を行う企業は、多額の補助金や税制優遇の対象となる。大熊町独自の補助金制度も存在する
- 大熊町のビジネス機会と支援体制
- 大熊町では、企業の進出を促すため、手厚い優遇制度が用意されている。最大30億円(中小企業は3/4補助)、または最大7億円(中小企業は2/3補助)といった大型の補助金制度や、税制優遇が存在する。これにより、企業は自己資金の持ち出しを大幅に抑えて事業を開始できる金銭的なメリットがある
- 事業計画の策定支援から、町や地元企業との交渉、さらには国や県、金融機関との連携まで、包括的なサポート体制が提供される。採択率が低い補助金の申請サポートや、数十億円規模の融資支援も行い、企業の事業実現を強力に後押しする
- トヨタ自動車が最大30億円と7億円の補助金を活用しバイオエタノール生産の研究開発を行う事例や、コネクトアラウンド社が立地補助金を受けて2025年6月に農業と食を一体化させた複合施設を開設した事例がある。他にも大林組や東芝などが実証実験を行っている
- 大熊町の最大の魅力は「ゼロから町を創れる」という特殊な環境にある。既存のしがらみがないため、他の地域では不可能な挑戦ができる。町自体も裕福で、企業からの提案を積極的に受け入れながら、理想の町づくりを共に進めていけるという、他に類を見ないステージにある
- 黒田氏は「復興のため」という理由だけでなく、純粋にビジネスチャンスの観点から大熊町の魅力に惹かれて移住した。東京よりも多くの事業に挑戦できる可能性を感じており、ビジネスの観点から見ても非常に魅力的な場所であると強調している
パネルディスカッション(という名のぶっちゃけトーク) – 地方と復興の現場から – イノベーションは『辺境』で生まれる を議論する
- インキュベーションセンターの3年間の歩みと地域の課題
- 初初年度の入居企業約百社のうち、初期の30社強の9割は運営者の知人関係だった。2年目以降は、既存の入居企業からの紹介や、国・県が実施する誘致プログラム経由での参加が中心となり、PRせずとも企業が集まる状況になっている
- 課題として、指定の6分野以外の企業は優遇措置を受けにくい。労働集約型の事業や医療系の事業は人手不足で難しい。住民票上は1万人がいるが、多くは避難しており住民参加型の実証実験は困難。土地は広く見えても、除染未了や利用制限で使用できない区域も存在する
- 町は「課題だらけ」であり、どの課題から手をつけるべきか優先順位を決められていないのが現状。明確なグランドデザインも存在しない。そのため、現在、本当に解決すべき課題は何かをヒアリングし、外部からの提案を募るための準備を進めている段階である
- 大熊町の復興とイノベーション
- 町の最重要目標は居住人口の増加であり、産業誘致はそのための安定した雇用を創出する手段と位置づけられている。しかし、町が打ち出すビジョンはまだ漠然としており、より明確な方向性が求められている。規制緩和については、町は柔軟な対応の準備があるものの、具体的な要望がまだ出ていない状態である
- 産業誘致の基本計画として、インキュベーションセンターと投資会社(ベンチャーキャピタル)の設立が両輪として構想された。しかし、議会で投資会社設立案は否決された。この構想は諦められておらず、現在は大熊町単独ではなく浜通り全体でのファンド立ち上げなど考えていきたい
- インキュベーションセンターでは、入居企業間の連携が自然に生まれるわけではない。そのため、年に数回の交流イベントの開催や、相性の良い企業同士の個別紹介、メディアでの入居者インタビュー発信といった意図的な仕掛けを行っている。これらの活動を通じて、事業者間の連携事例も生まれている
- 黒田氏は住民票を大熊町に移したことで、自治体からの信頼度が上がり、住民でなければ参加できない会議や得られない情報にアクセスできるようになった。コロナ禍でオンラインでの働き方が主流になったため、仕事の半分以上はオンライン会議で対応
- 東京から約5時間かかる交通の便が、企業誘致の大きな課題となっている。解決策としてヘリポートの建設が重要視されており、移動時間を1時間程度に短縮できると期待される
- 「辺境で生まれるイノベーション」に関する議論
- イノベーションは不便の解消から生まれるが、事業として成立するには市場と経済合理性が必要。そのため、辺境地での事業化は困難な場合が多く、人が多い都心部の方がビジネスは生まれやすい。大熊町のような課題先進地域での取り組みは、優遇制度や支援インフラといった特殊な条件が需要を創出しているため成立している
- 過疎地特有の課題を解決するビジネスモデルは、一つの地域だけで成立させるのは難しい。そのモデルを日本中・世界中の他の過疎地に横展開することで、初めて事業として成り立つ可能性がある
- 「辺境」という言葉は、物理的な遠隔地という意味だけでなく、「既存事業のような本流ではない領域」と解釈できる。新規事業は、こうした本流から外れた場所でこそ生まれやすいのではないかという視点が提示された
- 福島の新しいまちづくりにおける課題と展望
- 住民の多くが高齢者のため、移住者との融合は現状では考えにくい。2025年の大きなテーマとして、外部から進出した企業と地元企業との協業を推進。連携を促進するためのイベントを2025年から開始し、企業同士のコラボレーションを進める
- 企業の目的(事業成長)と自治体の目的(住民満足度向上)にはどうしても隔たりがでることがあり得る。補助金がなくなると企業が撤退するケースが多く、両者を結びつける継続的な仕組みが課題。町のファンド設立や、定着を促す制度設計を検討しているが、まだ試行錯誤の段階にある
- 2025年秋頃に町の予算で旅費を負担する「大熊町ツアー」を企画している
実施後に参加者からいただいたお声として、「黒田さんが現地に住民票まで移して活動されている話にはとても刺激を受けました」などのご意見をいただきました。ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!
今後とも継続的にセミナーを実施していきますので、ご興味のある方は、ぜひ、ご参加ください。
本記事に関するご質問やコメント、疑問に感じた点がございましたら、ぜひ、お問い合わせフォームよりご連絡ください。最後までお読みいただきありがとうございました。
一般社団法人日本イノベーション協会
事務局
高橋佑季