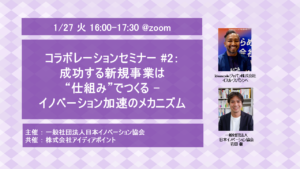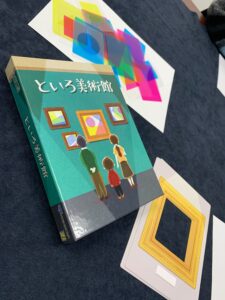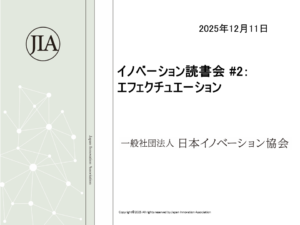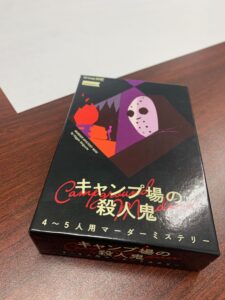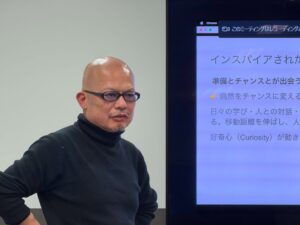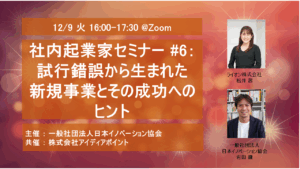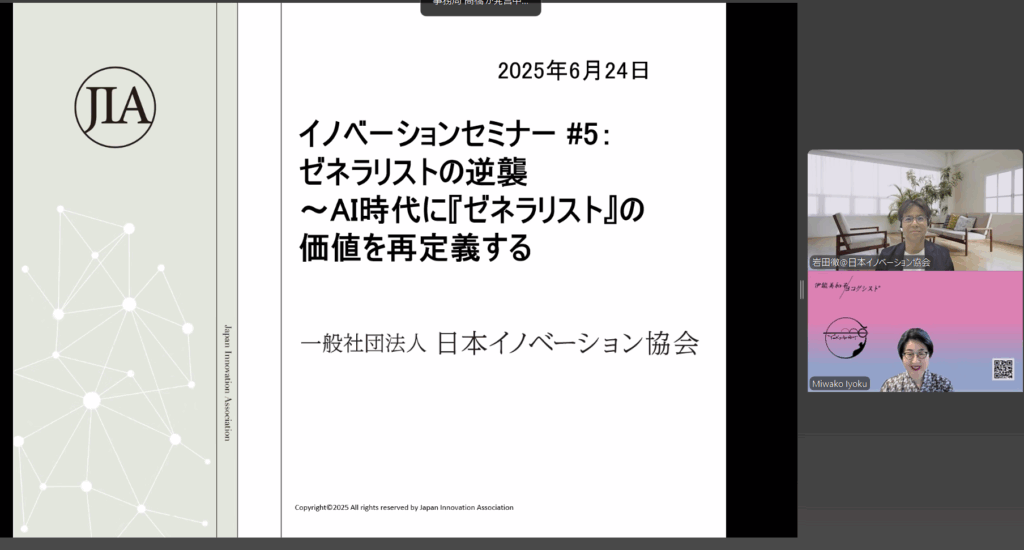
2025年6月24日(火)に「イノベーションセミナー #5: ゼネラリストの逆襲 ~AI時代に『ゼネラリスト』の価値を再定義する」を実施いたしましたので、ご報告いたします。
現在、日本イノベーション協会では、多くの企業で取り組んでいる『新規事業』、『イノベーション』について、その経験やスキルを共有する機会を提供しています。イノベーションセミナーでは、『イノベーションを起こす』ことに関するプロジェクトの推進経験のある方に、プロジェクトを推進する際の苦労や成功体験、『イノベーションを起こす』ために重要なことについてお話していただいています。
第5回目のテーマは「ゼネラリストの逆襲 ~AI時代に『ゼネラリスト』の価値を再定義する」です。今回は当協会の理事であり、株式会社Yokogushist代表取締役の伊能 美和子氏と当協会代表 岩田の対談を通じて、「ゼネラリストとその真の価値」について議論しました。当日の様子について報告いたします。
はじめに、当協会代表理事の岩田より、本イベントの趣旨と進行の説明をさせていただきました。その後、伊能氏より「AI時代に『ゼネラリスト』の価値を再定義する」についてお話いただき、その後、「イノベーションを起こすゼネラリストとは」についてパネルディスカッション形式で、当日、参加者様よりいただいたご質問も交えながら、伊能氏と岩田で対談をいたしました。
下記に、本イベントのサマリーをご報告いたします。
AI時代に『ゼネラリスト』の価値を再定義する(株式会社Yokogushist 伊能 美和子氏)
- 伊能氏のゼネラリストとしての原点とこれまでの歩み
伊能氏は、NTTグループという大企業において、多様な職種を経験してきた。あるタイミングであらためて振り返る中で『新規事業創出』という軸が一貫して存在していたことに気がついたという。
この『気づき』が、自らのこれまでのキャリアの意味づけと、ゼネラリストとしての強みの言語化につながった。伊能氏は自身を「ヨコグシスト®」と定義している。これは、業界や組織の枠を越えて、人と人、知と知をつなぐ“横串”の機能を果たす存在を意味する。専門性の深さではなく、つなぐ力、翻訳する力、複数の視点を持つことが、ゼネラリストの本質的価値であると考えている
- ゼネラリストの強みとタイプ
現代の労働市場では、年功序列や終身雇用といった従来の雇用慣行が変化し、ゼネラリストも実績を示すことが求められている。伊能氏は、ゼネラリストの利点として、多様な分野のプロフェッショナルと協働し、物事を多角的に捉え、全体最適を考える能力に長けている点を強調した。労働市場における人材タイプをスペシャリスト(追求型:縦軸)とゼネラリスト(幅広い:横軸)に分け、幅広い知見を持ちつつ1つの分野で深い専門性をもつT型、幅広い知見をもちつつ異なる分野の2つ以上の深い専門性をもつπ型、そして1つの分野で深い専門性をもちつつ他分野の専門家と繋がり成果を創出するH型があるのではないかとの説明があった
- シン・ゼネラリストになるための7つのポイント
AI時代に活躍し続ける「シン・ゼネラリスト」になるためには、以下の7つのポイントが重要だと考えられる
- 現職での経験を他でも使える形で磨き上げる
- 異業種・異分野の人脈を意識的に構築・交流する
- 強みを言語化・ブランド化して発信する
- AIを相棒・スタッフとして使い倒せる力をつける
- 学び続ける力を身につける
- 巻き込み力と問いの力で共創できる力を磨く
- 成果・価値を「見える化」して発信し続ける
- 副業とポートフォリオ型キャリア
自身の枠を広げる方法として、伊能氏は副業を推奨している。副業が難しい場合は、ボランティア活動(プロボノ)も有効であると述べ、自身がデジタルサイネージコンソーシアムでボランティア活動をしていたことを例に挙げた。今後は、一つの仕事に縛られず、複数の職業やプロジェクトを並行して行う「ポートフォリオ型」の働き方が主流になると予測している - AIとの共存と「マルチ・ポテンシャライト」
AIとシン・ゼネラリストは相性が良い。シン・ゼネラリストが持つ①幅広い知識・文脈の把握力、②問題発見・問いの設計力、③つなぎ合わせる力、④迅速なピボット力はAIのプロンプト作成において非常に有効だからだ。AIはゼネラリストの強力な「バディ」となり、能力を最大限に引き出すことができる。人生を「POC(Proof of Concept)」と捉え、思いついたことは小さく試すことが重要。また、TEDの「マルチ・ポテンシャライト(複数の潜在能力を秘めた人)」の概念を紹介し、アイデア統合力、高速学習能力、適応能力がシン・ゼネラリストの強みそのものであると述べた
パネルディスカッション(という名のぶっちゃけトーク) – イノベーションを起こすゼネラリストとは
- ゼネラリストの自己認識とキャリアの不安
伊能氏は、同じ会社に長く勤めるゼネラリストが、自身のスキルが他社で通用するのかという不安を抱えることに共感した。自身もNTTの子会社や合弁会社での勤務を通じて「他流試合」を意図的に経験してきたが、転職となると自信がなかったと語る。NTTにはフィットしていたものの、完璧ではなかったとも振り返り、ゼネラリストの悩みが「自分にはスペシャリティがない」という感覚から来ることが多いと示唆した - ゼネラリストの価値を高める視点
大企業のゼネラリストが様々な経験を積めることについて、その経験がプラスに働く人とマイナスに働く人がいるという点について、伊能氏は、その違いは「社会に新しい価値を作る」という一貫したテーマの有無にあると語った。大企業のリソースを活用し、自身のスキルや人脈で社会課題の解決を目指すという明確な目標を持つことで、経験が単なる「物知り」で終わらず、具体的な成果につながると説明した。また、自身の成果を言語化し、プロジェクトにおける具体的な役割を伝えることの重要性を強調した - AI活用と自己成長への工夫
伊能氏は、AIを自身の「相棒」として積極的に活用していると語った。AIは指示の変更に対しても嫌な顔をせず対応するため、指示自体を試行錯誤的にすることも可能で、部下への指示出しの煩わしさがなく、効率的な作業が可能になると話した。伊能氏は自己成長のために、普段からFacebookに日記のように書き続けることで言語能力を高めていると明かす。さらに、お風呂でスマホを使いながら調べ物をしたりメモを取ったりするなど、日々の生活の中で工夫して自己成長に取り組んでいることを紹介した。新しいことに取り組む人にとって、社外の仲間からのアドバイスや議論が非常に重要であると述べた
「シン・ゼネラリスト」の価値、どのようにして「シン・ゼネラリスト」になるのか、そして「シン・ゼネラリスト」になることで、自身の活躍の幅がグンと広がることがよく分かる内容でした。
実施後に参加者からいただいたお声として、「何を成し遂げたか言えないのは、それなりの規模の会社で、ぜネラリストだったら、当然だということに気づかせてもらえました」、「AIが発達している中で、ゼネラリストの活躍の場が広がり、それに名前をつけたいという伊能さんのお話が大変参考になりました」などのご意見をいただきました。
ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!
今後とも継続的にセミナーを実施していきますので、ご興味のある方は、ぜひ、ご参加ください。
本記事に関するご質問やコメント、疑問に感じた点がございましたら、ぜひ、お問い合わせフォームよりご連絡ください。最後までお読みいただきありがとうございました。
一般社団法人日本イノベーション協会
事務局
高橋佑季